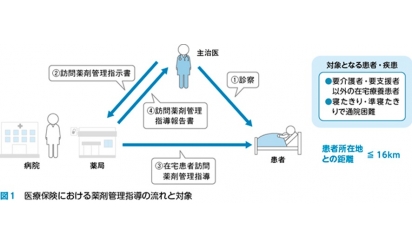メディカルサポネット 編集部からのコメント今回の「私の治療」では、山梨大学大学院医学工学総合研究部脳神経外科講師、吉岡秀幸氏と、同大学教諭の木内博之氏が脳内出血の治療の基礎について解説します。 脳卒中の中で、脳梗塞の次に多いのが脳内出血で、約2割を占めます。その脳内出血は約8割が高血圧性脳出血と言われています。 |
▶診断のポイント
脳内出血の症状は,血腫の存在部位と大きさによって異なる。頭痛,嘔気や出血部位に応じて,半身麻痺,感覚障害,半側空間無視,共同偏視,視野障害などの神経症状が出現する。出血が大型の場合には意識障害を伴う。
来院後は,バイタルサインの評価や神経診察後に頭部CT検査を行う。CTにより,急性期の出血は高吸収域として描出され,さらに,合併する脳室内出血,脳浮腫(出血後数時間で出現),脳ヘルニアの程度も把握することができる。
高血圧症の既往がない例,若年者,皮質下出血,くも膜下出血などを伴う場合は,出血源として,脳動静脈奇形,脳動脈瘤あるいは脳腫瘍からの出血の可能性も考え,3D-CT血管撮影,MRI/MRA,脳血管撮影検査などを行う。
▶私の治療方針・処方の組み立て方
脳内出血と診断したら,適切な血圧管理と頭蓋内圧管理を含めた内科的治療を行い,意識障害が中等度以上〔Japan Coma Scale(JCS)が20以上〕であれば,救命を目的に外科的治療を考慮する。
▶治療の実際
【内科的治療】
〈血圧管理〉
急性期治療では,できるだけ早期に収縮期血圧を140mmHg未満に低下させ,7日間維持することが推奨される2)。急性期に用いる降圧薬としては,カルシウム拮抗薬あるいは硝酸薬の点滴静注が勧められる。嚥下機能に問題がなければ,内服薬への切り替えを考慮してもよい。
▶ 一手目 :ペルジピンⓇ注(ニカルジピン塩酸塩)1回1~2mg (静注),必要な場合は引き続き,ペルジピンⓇ注(ニカルジピン塩酸塩)0.5〜6µg/kg/分(持続点滴静注),またはヘルベッサーⓇ注(ジルチアゼム塩酸塩)5〜15µg/kg/分(持続点滴静注)
〈頭蓋内圧管理〉
頭蓋内圧亢進症状を有する場合や,画像上,周囲の圧迫がみられ,それによる神経症状があるときには高張グリセオールの静注を行う。
▶ 一手目 :グリセオールⓇ注(濃グリセリン・果糖)1回200mL 1日2〜4回(点滴静注)
〈全身管理〉
ストレス性胃・十二指腸潰瘍(クッシング潰瘍)の頻度が高いため,抗潰瘍薬の投与を行う。
【外科的治療】
外科的血腫除去術は,①被殻出血では,意識障害が中等度(JCS 20〜200)で血腫が30mL以上かつ血腫による圧迫所見が高度な場合,②小脳出血では,直径3cm以上あるいは血腫が脳幹を圧迫し脳室閉塞による急性水頭症が生じている場合,③皮質下出血では,血腫が表在性で意識障害が中等度の場合,に考慮する。
血腫除去は,開頭手術,神経内視鏡手術あるいは定位的血腫除去術を状況に応じて選択する。急性水頭症には脳室ドレナージ術を行うことがある。深昏睡例(JCS 300)の予後はきわめて不良であり,手術適応とはならない。
【リハビリテーション】
全身状態に十分配慮した上で,急性期から積極的にリハビリテーションを行う。
【文献】
1) 国循脳卒中データバンク2021編集委員会, 編:脳卒中データバンク2021. 中山書店, 2021, p20-7, p101-4.
2) 日本脳卒中学会 脳卒中ガイドライン委員会, 編:脳卒中治療ガイドライン2021. 協和企画, 2021, p154-6.
吉岡秀幸(山梨大学大学院医学工学総合研究部脳神経外科講師)
木内博之(山梨大学大学院医学工学総合研究部脳神経外科教授)
<PR>マイナビの医療介護関連人材紹介サービス問合せはこちら
出典:Web医事新報
- 採用のご相談や各種お問合せ・資料請求はこちら【無料】
Parts:
内容:お役立ち資料