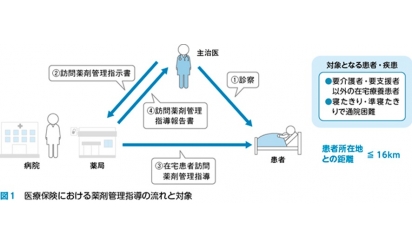メディカルサポネット 編集部からのコメント井上真奈美 国立がん研究センター がん対策研究所副所長が、井上 茂 東京医科大学公衆衛生学分野主任教授に、運動や身体活動が健康寿命の延伸にどう関わるのか、質問したところ、脳心血管病、一部のがん、骨粗鬆症、うつ病などを予防し、健康寿命を延伸させるというお返事でした。詳しくはぜひ本文をお読みください。 |
運動や身体活動は疾患横断的予防や健康寿命の延伸にどう関わるのでしょうか。余暇や仕事,日常でどのような運動や身体活動がよいのか最近の知見やガイドラインについてご教示下さい。
東京医科大学・井上 茂先生にご解説をお願いします。
【質問者】井上真奈美 国立がん研究センター がん対策研究所副所長
【回答】
処身体活動量が多い人では,死亡率が低く,糖尿病,虚血性心疾患,脳血管疾患,がん,骨粗鬆症,うつ病などの罹患率の低いことが報告されています1)。がんの部位別には大腸がん,乳がんの予防効果が確実とされています。一般に疫学研究では罹患率の高い疾病からエビデンスが出てきますので,今後は罹患率が低い部位のがんについても検討が進むことでしょう。また,高齢者では身体機能を維持・向上する効果があり,介護予防,QOLの向上,健康寿命の延伸が期待できます。認知機能低下の予防効果については,WHOの身体活動ガイドラインも含めて「効果あり」と記載されている資料が多数ありますが,学術的にはまだ議論の残る段階です。
推奨される身体活動量について,WHOは150~300分/週の中高強度身体活動(moderate to vigorous physical activity:MVPA)を推奨しています。また,300分/週以上でさらなる効果が期待できることを示唆しています。ここで,中高強度は3METs(普通速度の歩行に相当)以上の強さを意味しています。一方,日本の厚生労働省はMVPAを23METs・時/週以上行うことを推奨しています。これは,60分/日以上のMVPA,あるいは8000歩/日以上に相当する身体活動量です。ただし,この基準を満たせない場合であっても,現在の生活に10分のMVPAを加えることの効果を強調しています。WHOと日本の推奨値の違いについては,日本人は身体活動量が多くWHO等の海外の基準値では既に達成している人が多いため,と説明されています。
一方,臨床系の運動療法ガイドラインでは毎日30分程度の運動療法が推奨されています。これらは日常生活での身体活動に加えて実施する「運動」に主眼があると理解するのが適当です(実際に30分間歩いても3000〜4000歩程度にしかなりませんから,これだけでは成人の運動量としてはもの足りないことがご理解いただけると思います)。したがって,運動療法以外の時間が不活動にならないように注意が必要です。
このほかに,レジスタンス運動,柔軟運動,バランス運動などに関する基準が国内外のガイドラインに示されています。有酸素運動のみならず,身体活動・運動もバランスよく実施することで多様な効果が期待できます。
最後に,近年話題となっている座位行動についてです。座りすぎは,単純に身体活動の裏返しのようにも思えますが,話はそれほど単純ではありません。座りすぎに関する研究においては,①これまで推奨されてきたような中高強度ではない,ごく軽い身体活動(たとえば,立ち仕事など)にも効果があること,②座ったまま長時間過ごすことそのものが良くないこと(こまめに座位時間をブレイクする必要があること),を意味しています。1日の座位行動を8時間以下にするというガイドラインをカナダ政府が示していますが,この領域の研究は今後さらに活発になると思われます。
【文献】
1)2018 Physical Activity Guidelines Advisory Committee Scientific Report. Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, 2018.
https://health.gov/sites/default/files/2019- 09/PAG_Advisory_Committee_Report.pdf
【回答者】
井上 茂 東京医科大学公衆衛生学分野主任教授
出典:Web医事新報
- 採用のご相談や各種お問合せ・資料請求はこちら【無料】
Parts:
内容:お役立ち資料