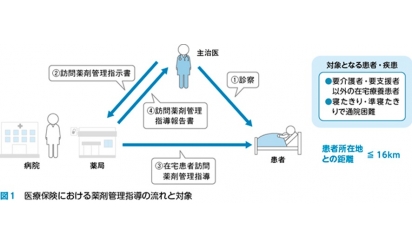メディカルサポネット 編集部からのコメント日本では人口比で高齢者の数が増え、超高齢社会となっています。 その中で、今後も増え続ける独居高齢者の患者さんと向き合うにはどうしたらいいのか。 多職種連携のポイントや、家族への助言、在宅で生じやすい問題点と対処法について、森 清東大和ホームケアクリニック院長/在宅サポートセンターセンター長が簡潔にまとめました。 |
▶アセスメントのポイント
入院患者の場合,退院時に独居生活が可能であるかの判断は,常に困難である。リスクを整理し,退院カンファランスを行い,危険が生じた場合・本人が意思を変更した場合・予期される治療可能な合併症が生じた場合などには再入院/緊急入所すること等を想定内として,リスクを共有することは大切である。試行錯誤が必要なこともある。訪問診療や訪問看護は,初回訪問前に少し長めの事前面談を家族または市役所など自治体担当職員とすることが好ましい。全盲であっても,寝たきりであっても,本人が望み,条件が整えば,自宅での生活が可能であり,在宅看取りも可能である1)。
▶緊急時の対応
本人から訪問看護や家族等への連絡方法の確認,毎日の本人の安否確認,キーボックス(またはそれに変わる方法)の確認を事前に行う。本人が最期はどうしたいのかなどの意思確認をした上で,どのようなときに入院を選択する可能性があるのかを本人・家族と相談し,事前に決めておく。入院先,入院方法も事前に決めておき,それらが困難である場合,本人/家族または自治体へ,リスクの説明とその了解が必要となる。
▶長期管理・経過観察上の臨床的注意点
本人の意思・生活の上での幸福(ものがたり)を確認しつつ,生きがいの継続をめざす。様々な地域資源の活用を検討する。
▶主治医としてやるべきこと
多職種が生き生きと奉仕できるように調整するとともに,すべてのスタッフの健康にも配慮する2)。自治体との連携などを率先する。本人が無縁(孤立無縁・天涯孤独)であると主張していても,連絡すべき親戚がいることもあり,自治体には調査と責任を負ってもらう。
▶多職種連携のポイント
「認知症のある一人暮らしの高齢者」「重症心不全を持つ一人暮らし高齢者」などへのケアにはコツがあり,入浴・服薬・清潔・栄養・リハビリテーションなどについて,地域でマニュアルを共有することも好ましい。地域全体の多職種の関わりが必要であり,ヘルパー,ケアマネジャー,訪問入浴,ソーシャルワーカー,訪問看護師,訪問薬剤師,訪問栄養士,訪問リハビリテーション,傾聴ボランティア,見守り・声かけ活動,などの関わりの有効性を確認する。その上で,セルフネグレクトと災害時対策を含めた地域包括ケアシステムがあることを確認する。多くの苦労をともにしつつ,在宅看取りをした場合,チーム(スタッフ)の癒やしのために,デスカンファランス(スタッフへのグリーフケア)は有効である。
▶制度面の知識
成年後見人がいる場合には,各種支払いの援助のほかに,「身上監護」として本人の意思の実現を手伝ってもらう。
▶家族への助言
これから生じることについての説明を事前に行う。本人の意思を受容していることの確認と,家族の負担や利害関係を整理する。各種支払いについては,本人・家族・地域包括支援センターと相談しておく。
▶在宅で生じやすい問題点と対処法
死亡診断書の提出者と葬儀については,戸籍法と墓地,埋葬等に関する法律から必要事項を確認し3),関係者には事前に説明しておくことも大切である。
▶社会資源の活用
一人暮らしの高齢者は,どの地域でもめずらしいことではなくなっており,各市町村で独自の対応をしていることもある。自治体・地域包括支援センター・社会福祉協議会・ケアマネジャー・関連する地域NPO,地域自治会/老人会,コンビニエンスストア,商店街などとも,日頃からの連携があることが好ましい。問題点や課題を見つけた場合には地域ケア会議の議題とし,地域包括ケア推進会議で認識を共有し,地域の改革・発展をめざすべきである。
【文献】
1)森 清, 編:カンファランスで学ぶ多職種で支える一人暮らしの在 宅ケア. 南山堂, 2019, p28-46.
2)森 清:のこされた者として生きる 在宅医療, グリーフケアからの気付き. いのちのことば社, 2007, p20-9.
3)森 清:ひとりでも最後まで自宅で. 教文館, 2019, p127-34.
森 清(東大和ホームケアクリニック院長/在宅サポートセンターセンター長)
出典:Web医事新報
- 採用のご相談や各種お問合せ・資料請求はこちら【無料】
Parts:
内容:お役立ち資料